
みなさん、こんにちは。
ライフカウンセリングSORAの関口です。
平成28年度の『通信利用動向調査』が総務省から発表されました。
通信利用動向調査とは、日本国民の通信サービスの利用状況や情報通信関連機器の保有に関する調査です。
今回の『通信利用動向調査』では、スマートフォンを保有する個人の割合は56.8%、インターネットの利用目的では、20代の3分の2超が、SNS・動画投稿を利用しているとの調査結果になりました。
この調査結果を裏付けるように、電車内の光景を見ると、ほとんどの人がスマホを操作しています。
また、今は小学生でもスマホを持ち、LINEや動画投稿をしています。
インターネットやスマホは大変便利なツールです。
もちろん、私も毎日スマホを使用しています。
しかし、スマホは便利な反面、脳を抑制し「いま」という時間を浪費するツールでもあることをご存じですか?
「歩きスマホはやめましょう、運転中のスマホ操作は危険です」と毎日のように耳にしますが、それでも事故が減らないのはなぜでしょうか?
それは、スマホやSNSの操作により「脳が抑制され、いまが奪われている」からです。
今回は、私達が日々便利に使用しているスマホやSNSが及ぼす「マイナスの影響」について書いていきます。
スマホを見つめる人々

先日、息子とファストフード店に入りました。
息子と食事をしている時、隣に2人の男子高校生が座りました。
その高校生たちは、片手でスマホを操作しながら、もう片方の手でハンバーガーを食べ始めました。2人で会話をすることなく、お互いがお互いのスマホ画面を見ながらの食事。
しばらくして、1人の高校生が「お前のラインのグループ数はどれくらい?」と質問をしました。
質問をされた子は「俺は10グループぐらい、お前は?」と聞き返したところ「俺は30グループあるよ」とその子は自慢げに答えていました。
食事中の2人の会話はそれきりで、食べ終えた後は直ぐにお店を出ていきました。
彼らは友人との食事の時間を楽しめていたのでしょうか。
食事を「おいしく」いただくことができたのでしょうか?
最近の子どもは、電車の車内でおとなしくスマホを見ています。
車内で子どもがスマホを見ていてくれればおとなしくしているので、親とすればとても助かります。
しかし、私が子どもの頃は、電車に乗ると、子どもは靴を脱ぎ反対側を向いて流れゆく車窓を楽しんでいたものです。
今の子どもはどうして車窓を見ようとしないのでしょうか。
昔に比べ車窓がつまらなくなったのでしょうか、それとも、子どもが車窓を楽しめなくなったのでしょうか?
スマホで記憶が消える

脳トレで有名な「東北大学の川島先生」の研究によると
「スマホでSNSなどをしていると、見た目には手を動かしたり、頭を使ったりして脳を刺激しているように思えても、脳を測定すると抑制状態、つまり眠った状態」になっているそうです。
「7年間の研究結果では、スマホやSNSの利用と学力の関係が明らかになってきており、研究で分かったのは、スマホやSNSを使えば使うほど睡眠時間や勉強時間に関係なく、学力が下がる。例えば、家で全く勉強をしていない子供達のグループがあります。
スマホをいじらない子はある程度点が取れるのですが、その先、スマホを使い始めると睡眠時間は一緒でも、そこから点が下がっていく。要はスマホを使ったことによって、脳の中の学習した記憶が消えたということです。
記憶力を高めていくには、感覚や情報を使う事が大切であり、読書の時に目で追うだけではなく、声に出す、手で書くというように視覚、聴覚、運動情報を多く使った方が記憶に残りやすいそうです」
また、「SNSはよくコミュニケーションツールという言い方をされますが、SNSでやり取りする相手が人間ではなく人工知能を備えた機械であっても、そうとは気づかない、人だと思ってやりとりをしてしまうという具体的なデータがある。つまり、人と人とのコミュニケーションが担保されていない」
※参考文献 月刊誌 『致知』 2016年12月号 「素読のすすめ」より
川島先生は「人間の脳」と「スマホやSNS」の観点から問題点を指摘しています。
次に元ITエンジニアの私の視点から、スマホと「いま」について考えてみたいと思います。
スマホに「いま」を奪われる

なぜ多くの人が「歩きスマホをしてしまう」のでしょうか?
誰もが「歩きスマホが危険」であることをわかっています。
それなのに、歩きスマホをやめられないのは、その人の「いま」が「スマホに奪われている」からです。
私がITエンジニアをしていた頃のデータ通信速度は速くても128kbpsでした。
あれから約10年後、現代のスマホの通信速度は理論上で150Mbpsまで出せるようになりました。
128kbpsと150Mbpsの速度の差を車の時速で例えるならば、10年前は時速128km/hで通信データを運んでいたトラックが、現代では時速150,000km/hで走れるようになりました。
また、運ばれてくるデータを処理するスマホ本体の性能も大幅に向上したことにより、私達はスマホで「リアルタイム通信」ができるようになりました。
スマホのリアルタイム通信が可能になったおかげで、私達の目の前に2つのリアルが登場しました。
それが、実際の「リアル」とスマホの画面内の「バーチャルリアル」です。
人間の脳は「2つのこと」を同時に意識することや考えることはできません。
朝ご飯と晩ご飯を、過去と未来を同時に考えることもできません。
「リアル」と「バーチャルリアル」の両方を同時に意識することもできません。
歩きスマホをしてしまう人の意識は「バーチャルリアル」が優先されています。
「バーチャルリアル」が優先されるから、実際の「リアル」が疎かになり事故を起こしてしまうのです。
友人との食事中にスマホを見続けていた高校生。30もの「ライングループ」に所属していれば、きっと彼のスマホには「ライン通知」が頻繁に届くことでしょう。
ライン通知が届けば届くほど、彼の意識はスマホに向けられることになり、彼の「いま」が奪われてしまう。
電車の中で、おとなしくスマホを眺めている子ども。
昔も今も、車窓を流れる景色(リアル)は変わらないのに、スマホの画面内のバーチャルリアルを楽しむ子ども達。
僕が子どもの頃、流れゆく車窓を見て楽しかった。
「このまま電車に乗っていたらどこまでいけるのだろう?」と「子どもらしい空想」することが楽しかった。
スマホを眺めている子どもは、果たして「子どもらしい空想」をすることができるのでしょうか。
スマホを使うことで、誰かとつながり、暇な時には、動画を観たりゲームができたりする。
確かにそれは、楽しいのかもしれません。
しかし、その反面にスマホを使うことで脳が抑制され、記憶力も想像力も低下し、リアルの「いま」が奪われていく。
私達はどこの「いま」を生きているのでしょうか?スマホの画面の中の「バーチャルリアル」でしょうか、それとも自分の目の前の「リアル」なのでしょうか。
今回のスマホの記事を書いているとき、ミヒャエル・エンデの『モモ』を思い出しました。
ミヒャエル・エンデが伝えようとしていた時間貯蓄銀行の「灰色の男」とは「スマホ」のことなのかもしれません。
「モモ」の言葉

ミヒャエル・エンデの「モモ」は「時間」をテーマにした物語です。
「モモ」に登場すると時間貯蓄銀行の「灰色の男」は様々な誘惑を行い、町の人の時間を奪っていきます。
「灰色の男」に時間を奪われた大人達は、忙しく働くようになりました。
大人達は、余暇の時間でさえ少しの無駄もなく使わなくてはと考えました。
ですから、その時間のうちにできるだけたくさんの娯楽を詰め込もうと、もうやたらとせわしなく遊ぶのです。
だから、もう楽しいお祭りであれ、厳粛な祭典であれ、ほんとうのお祭りはできなくなりました。
夢を見るなど、ほとんど犯罪も同然です。
けれど一番耐えがたく思うようになったのは、静けさでした。
自分達の生活が本当はどうなってしまったのかを心のどこかで感じとっていましたから、静かになると不安でたまらないのです。
ですから、静けさがやってきそうになると、そうぞうしい音をたてます。
けれども子どもの遊び場のような楽しげなさわぎではなく、怒り狂ったような、不愉快な騒音です。
この騒音は日ごとに激しくなって、大都会に溢れるようになりました。
仕事が楽しいとか、仕事への愛着を持って働いているかなどということは、問題ではなくなりました。
もしろ、そんな考えは仕事のさまたげになります。
大事なことはただひとつ、できるだけ短時間に、できるだけ沢山の仕事をすることでした。
~ミヒャエル・エンデ『モモ』より引用~
「灰色の男」に時間を奪われた大人達。
大人は子供と遊ぶ時間がなくなりました。
その代わり大人は子どもに高価なおもちゃを与えるようになりました。
「とりわけ、こういうおもちゃは細かなところまで至れり尽くせりに完成されているために、子供が自分で空想を働かせる余地が全くありません。
ですから、子供たちは何時間もじっと座ったきり、ガタガタ、ギーギー、ブンブンとせわしなく動き廻るおもちゃの虜になって、それでいて本当は退屈していて眺めてばかりいます。けれど。頭の方が空っぽでちっとも働いていないのです」
~ミヒャエル・エンデ『モモ』より引用~
「灰色の男」の死んだ時間を人間が受け取ると、人間「致死的退屈症」という病気になる。
「はじめのうちは気付かない程度だが、ある日急に何もやる気がなくなってしまう。
何についても関心がなくなり、何をしても面白くない。
この無気力はそのうち少しずつ激しくなっていく。
日毎に時を重ねるごとにひどくなる。
気分はますます憂鬱になり、心の中はますます空っぽになり、自分に対しても世の中に対しても、不満が募ってくる。
そのうちに、こういう感情さえなくなって、およそ、何も感じなくなってしまう。
何もかもが灰色で、どうでもよくなり、世の中はすっかり遠のいていてしまって、自分とはなんの関わりもないと思えてくる、怒ることもなければ、感激することもなく、喜ぶことも悲しむこともできなくなり、笑うこともなくことも忘れてしまう。
そうなると、心の中は冷え切ってもう一切愛することができない。
ここまで来ると病気は治る見込みがない。後に戻ることはできないのだよ。
うつろな灰色の顔をしてせかせかと動きまわるばかりで、灰色の男とそっくりになってしまう。
そう、こうなったらもう灰色の男そのものだよ。この病気の名前はね、致死的退屈症というものだ」
~ミヒャエル・エンデ『モモ』より引用~
「致死的退屈症」は現代でいうところの「スマホ依存症」のことではないでしょうか。
本当の楽しさ

スマホは、いつでも知りたい情報だけを調べられ、どこでも面白いゲームや動画を観ることができ、誰とでもコミュニケーションを交わすことができます。
一方、スマホは細かなところまで至れり尽くせりに完成されているために、脳が抑制され想像を働かせることができません。
では、脳が抑制されているのに、なぜスマホを使い続けてしまうのでしょうか?
それは、スマホの刺激的で受動的な楽しみ(快楽)は依存性が高く、次の快楽を求めてしまうからです。
YouTubeで動画を1本みたら次から次へと観てしまい、気づいたら1時間経過していたという経験は、みなさんありませんか?
人間が感じる楽しさには2つあります。
ひとつが映画や動画を観て感じる「受動的な楽しさ」、もうひとつが、自分の心の中から涌き起こる「能動的な楽しさ」です。
そして、心の底から涌き起こる「能動的な楽しさ」が本当の楽しさです。
モモに登場する道路清掃人のベッポじいさんの言葉を紹介します。
なあモモ、とっても長い道路を受け持つことがあるんだ。
恐ろしく長くてこれじゃとてもやり切れないと思ってしまう。
そこで、せかせかと働きだす。
どんどんスピードを上げていく、時々目を上げて見たのだが、いつ見ても残りの道路は減っていない。
だから、もっとすごい勢いで働きまくる。心配でたまらないのだ。
そして、しまいに息が切れて動けなくなってしまう。でも道路はまだ残っているのだ。
こういうやり方はいかんのだ。1度に道路の全部のことを考えてはいかん。
わかるか?次の1歩ことだけ、次のひと呼吸のことだけ、次のひと掃きのことだけを考えるのだ。
いつも、ただ、次のことだけをな。すると楽しくなってくる。
これが大事なのだ。楽しければ仕事がうまくはかどる。
こういうふうにやらなきゃダメなんだ。
ひょっと気がついたときには、1歩1歩進んだ道路が全部終わっておる。
どうやってやり遂げたかは自分でもわからん意地も切れていない。これが大事なのだ。
~ミヒャエル・エンデ『モモ』より引用~
ベッポじいさんがいう「道路」を「人生」に置換えると大切なことが見えてきます。
人間が心の底から楽しいと感じるもの、それはスマホの画面の中にあるのではなく、いまの自分の周りにある物事のなかにあります。
家族や友人との楽しい食事、電車の流れゆく景色を見て、思い描く空想。そうした何気ない「リアル」の日常のなかに、本当の楽しさは隠れていると私は思います。
まとめ
情報化が進めば進むほど、仕事やコミュニケーションが効率化され、生活に「ゆとり」がうまれるといわれていました。
そして実際に「リアルタイム」通信まで情報化が発展してきましたが、私たちの生活に「ゆとり」がうまれたのでしょうか?
「ゆとり」がうまれるどころか、スマホや時間に追われるようになっていないでしょうか?
「時間をケチケチすることは、本当は全然別の何かをケチケチしていることに誰1人気づいていないどころか、自分たちの生活が1ごとに貧しくなり、日ごとに画一的になり、日ごとに冷たくなっていることを、誰1人認めようとしない。
けれど時間とは生きるということそのものなのです。そして、人の命は心を住処としていいのです。
人間が時間を節約すればするほど生活はやせ細っていくのです
これからも情報化は進んでいきます。
その時代変化のなかで、目的を持って便利にスマホを使う能力も必要です。
それと同時に、目の前にいる友人や家族のコミュニケーションを交わすこと、自分と対話する時間を確保すること、心から涌き起こる「楽しさ」を大事にしておかないと、心は「バーチャルリアル」の中に生きるようになり、やがて「致死的退屈症」にかかってしまいます。
「いま」という時間は人生に一度きりです。
その時間を「スマホのバーチャルリアル」に使うのか、それとも、あなたの「リアルの人生」として使うのか、これからは2つの生き方が問われる時代になると思います。
スマホは「使う」ツールであり「使われる」ツールではありません。
さあ、自分のリアルの「いま」を取り戻していきましょう。
お勧めの本
■ストーリーをとおして大切な「時間」が見えてきます
■スマホとSNSの問題を踏まえ、声を出して本を読む大切さが学べます
スマホ依存の関連記事
これから日本では、スマホ依存などの問題がより深刻化してくると考えられます。
自分自身が、大切な家族が、周りの人が、スマホ依存にならないようにご参考ください。






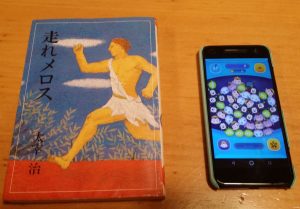



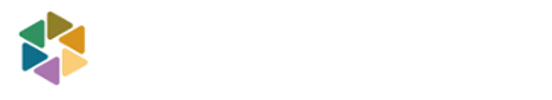
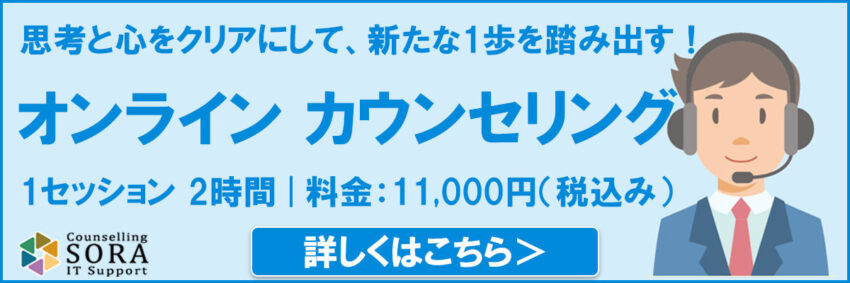



コメント
コメント一覧 (5件)
[…] 関連記事スマホから「記憶」と「いま」を取り戻そう […]
[…] 関連記事スマホから「記憶」と「いま」を取り戻そう […]
[…] 関連記事スマホから「記憶」と「いま」を取り戻そう […]
[…] 関連記事スマホから「記憶」と「いま」を取り戻そう […]
[…] スマホから「記憶」と「いま」を取り戻そう-心理カウンセリング 空|新宿・川越・オンライン より:2019年12月8日 6:00 午後 […]