みなさん、こんにちは。
ライフカウンセリングSORAの関口剛史です。
1人ひとりがスマホをもつようになり、SNSで誰とでもつながれる時代になりました。
SNSに投稿した文章や写真に「いいね」をしてもらえたり、アカウントをフォローしてもらえたりすると、自分のことを共感してもらえたような気持ちになりうれしいですね。
しかし、「もっと、いいねをもらいたい」や「フォロワーをもっと増やしたい」と思いはじめると、コミュニケーションは共感から強要に変わってしまうことをご存じですか?
今日は「共感コミュニケーションと強要コミュニケーションの違い」について書いていきます。
共感コミュニケーションと強要コミュニケーションのちがい
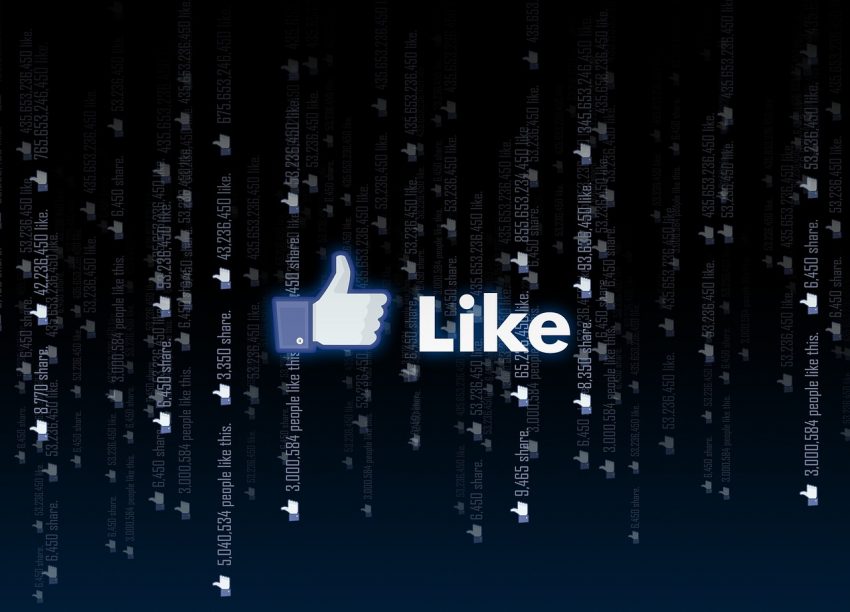
まず、共感と強要の言葉の意味から。
共感とは
他人の意見や感情などをそのとおりだと感じること。またその気持ち。
デジタル大辞泉より引用
強要とは
無理に要求すること。無理やりさせようとすること
デジタル大辞泉より引用
共感と強要の違いを一言で表すと、お互いの心が「わかりあえる」のが共感で、片方の心を「わからせようとする」のが強要。
共感コミュニケーションでは、聞き手(情報受信者)の感情が主で、強要コミュニケーションでは話し手(情報発信者)の感情が主になる。
例えば、Aさんが「インスタ映えしそうな写真」をアップしたとき、Bさんが心から「いい写真だな」と思い「いいね」をするのは共感コミュニケーション。
一方、同じ写真を見たCさんが「普通の写真だな・・・と思いスルー」、このときAさんが「なんで、Cさんは「いいね」してくれないの」と思うのが強要コミュニケーション。
人間は、私のことを「見てほしい・認めてほしい・わかってほしい」という欲求が心の中にもあるから、SNSで「いいね」や「フォロー」してもらえると「うれしい」と感じられる。
しかし、私のことを「見てほしい・認めてほしい」という思いが強くなればなるほど、強要コミュニケーションを求めたくなる。
強要コミュニケーションは、「いいね」をもらえてもすぐに次の「いいね」が欲しくなり、もっと「いいね」をもらえるように投稿が過激になったり、フォロワーを求めるばかりに自分を見失ったりする。
最近、SNSの動画投稿で問題が多いのは、強要コミュニケーションを求めすぎた成れの果てではないだろうか。
一方、共感のコミュニケーションでは、聞き手(情報受信者)の感情が主になる。
Aさんが心から「いいな」と思える写真をアップしたとき、Bさんが心からの「いいね」があれば、AさんとBさんは共感コミュニケーションになる。
また、Cさんの心に写真が響かず「いいね」がなくても、AさんはCさんとの違いを受け入れることができれば、お互い「感じ方は違う」という共感コミュニケーションにもなる。
共感コミュニケーションは、自分と相手の違いを受け入れたうえで、自分から素直な表現をすることで、うまれるコミュニケーション。
共感とは、相手に同じ気持ちになってもらうことではなく、私はこう思う、こう考えていると素直な表現をしたあとで、相手の心の中から「私もそう」と自然と湧き起こるもの。
素直な気持ちがわかりあえるから、お互いが心から「うれしい」や「つながり」を感じあえるもの。
1人ひとりがスマホをもつようになり、SNSで誰とでもつながれる時代になった。
しかし、最近のSNSは誰かと「つながる」ことよりも「見てもらう・認めてもらう」ことが優先になっていないだろうか?
共感という名の強要を求めていないだろうか?
自分で自分のことを見ても認めてもいないのに、どうして他者から見て認めてもらおうとしてしまうのだろうか。
自分のことを認めてもらうための強要コミュニケーションよりも、まずは、自分のことを自分で認めわかろうとしよう。
もしかしたら「こんな、ダメな自分を自分で認めることなんてできない」と思うかもしれない。
でも、まずはダメな自分もそのまま認めて受け入れてみよう。
いまの自分を素直に認め受け入れることができたとき、強要コミュニケーションから共感コミュニケーションに自然と切り替わる。
そして、共感コミュニケーションで「うれしい」や「わかりあえる」と感じることが増えてくれば、本当の意味での「つながり」を実感をすることができ、本当の自分を見つけることもできるから。
まずは、他者から「どう見られるか?」よりも、今の自分を素直に認めて受け入れてみよう!
まずは、素直な自分とつながってみよう!

まとめ
SNSは誰とでも気軽に「つながっている」ことでの安心感を得られると同時に、簡単に「切られる」ことへの不安感を抱くものです。
そして、「つながっている」ことの安心より「切られる」ことへの不安が大きくなったとき、「もっと、私のことを見て!認めて!」と強要コミュニケーションをはじめてしまいます。
でも、それは間違いです。
心が不安を抱くのは「SNSで誰かとつながれていないこと」ではなく「自分自身とつながっていない」からです。
自分自身とつながっていないから「自分がどう思うか?」よりも「他者からどう見られるか?」ばかりが気になるのです。
ありのまま自分を認めて、素直な共感コミュニケーションを意識していきましょう。
共感コミュニケーションは、素直な自分を相手にさらけ出すようで「怖い」と感じると思います。
しかし、素直な自分でつながれる相手こそが、本当の友人と言えるのだと、私は思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
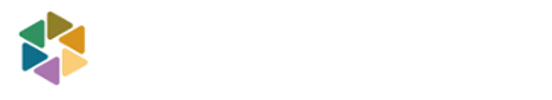
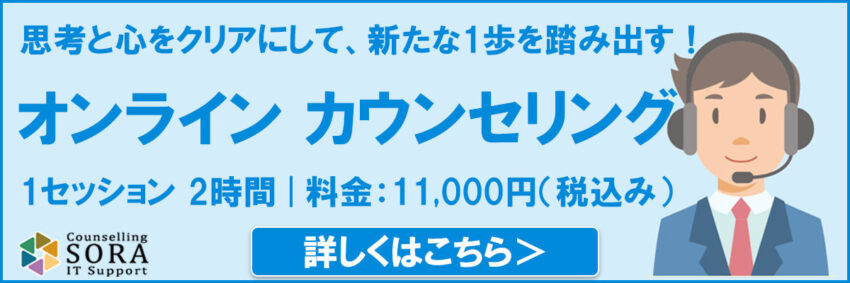

コメント
コメント一覧 (4件)
[…] 関連記事共感コミュニケーションと強要コミュニケーションのちがい […]
[…] 関連記事共感コミュニケーションと強要コミュニケーションのちがい […]
[…] 関連記事共感コミュニケーションと強要コミュニケーションのちがい […]
[…] 関連記事共感コミュニケーションと強要コミュニケーションのちがい […]