みなさん、こんにちは。
ライフカウンセリングSORAの関口剛史です。
先日、総務省より各携帯電話会社に対して5G(5世代移動通信システム)の免許が割り当てられました。
これにより携帯各社が5G 通信の導入に向けて動きだし、きっと近い将来5G通信があたりまえになり、すべての物がネットワークにつながるIoT(Internet of Things)化へ。
やがて、ネットワークで情報を得るようになった物がAIで物事を判断するようになります。
私たちの周りでは、すべてのものがつながりはじめ、とても早いスピードで情報が飛び交うようになりますが、もっと早く、もっと便利に、もっと効率的を求めたとき、その情報を扱う私たちの心は、そのスピードについていけるのでしょうか?
このままでは、人間は物事の結果のみを求めはじめ、目先のことばかりを考えるようになり、その結果、心にゆとりがなくなり、最後はAIに使われるようになると思います。
しかし、どんなに情報技術が発展しても、私たちの「心を育てる時間」は変わりません。
また、私たちの心を育てるには「プロセス」と「時間」が、今も昔も必要です。
そのことを二宮金次郎は「遠きはかる者は富む」と説き、ミヒャエル・エンデは「時間とは生きること」と説きました。
遠きはかる者は富む
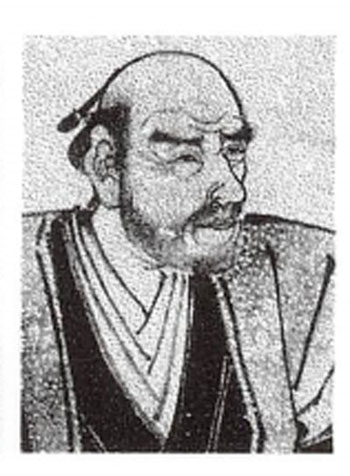
最初に二宮金次郎の「二宮翁夜話集」から「遠きはかる者は富む」をご紹介します。
翁のことばに、遠い先のことを考える者は富み、近まのことをばかり考える者は貧乏する。
遠い先のことを考える者は、百年の後のために松・杉の苗でも植える。
まして、春植えて秋みのるものなど当たり前のことだ。だから富有でいられる。
ところが目先のことばかり考える者は、春植えて秋みのるものさえ、まわりくどいといって植えないで、ただ眼前の利益に迷って、まかずにとり、植えずに刈るようなことばかりに目をつける。
だから貧窮するのだ。
まかずにとり、植えずに刈るようなものは、眼前の利益があるように見えるが、一度とったら二度と刈れない。
ところが、まいてとり、植えて刈るものは、年々歳々尽きることがない。
だから無尽蔵というのだ。仏教で「福聚(ふくじゅ)の海」というのもこれと同じ意味だ。
引用 二宮翁夜話(上) 発行:一円融合会刊 原著:福住正兄
時代が変わっても時間軸は変わらない

以前、農業イベントを企画していたとき、小学5年生の子どもから「麦なんてつくるの簡単だよね!」と言われたことがあります。
その子は自信満々の顔をしていたので、それまで「麦をつくるのは簡単である」と信じてきたようです。
「どうしてそう思うの?」と聞いたところ、子どもは「ゲームの中の麦づくり」と「実際の麦づくり」が一緒だと思っていました。

バーチャルリアルのゲーム中では、種を蒔いてから麦が育つのは7分で育つそうです。しかし、実際に麦を育てると6ヶ月かかります。
では、みなさんに質問です。
「麦は7分で育つ」と信じ込んでいる子どもと、「麦は6ヶ月かけて育つ」ことを知っている子どもとでは、ひとつのパンを食べたとき、どちらの子どもの方が「幸せや豊かさ」を実感できるでしょうか?
麦は7分で育つと信じて生きていると、パンを焼く3分を長く感じることでしょう、パンを残すことにも罪悪感を抱かないでしょう。
インターネット技術が普及し、すべての物がリアルタイムでつながるようになりました。
いつでもどこでも誰とでもつながることができて、現実の「リアル」とスマホ画面の中の「バーチャルリアル」の区別がむずかしい状況になり、多くの人が歩きスマホをやめられなくなりました。

そして、次は5G通信とIoT社会がはじまります。
通信はより高速化され、通信で情報を得た物がAIで物事を判断するようになり、その結果、物に使われる人が増えていくのではないでしょうか。
そして、人間は時間がかかるプロセスよりも、時間がかからない結果を求めるようになり、我慢することができず些細なことで逆ギレしてしまったり、辛抱することができずすぐに逃げ出したくなったり、人を騙してでも簡単な結果を得ようとするようになる。

でも、それは二宮金次郎の言うところ「まかずにとり、植えずに刈るようなもの」で、その結果は「眼前の利益があるように見えるが、一度とったら二度と刈れない」不毛のものになります。
このことを二宮金次郎は「心の貧乏」と農民に説いたのだと思います。
どんなに通信技術が高速化しても、麦が育つには6ヶ月かかるように、心を育てるにはそれなりの時間とプロセスが必要です。
それは二宮金次郎の時代と変わるこはなく、これから先の時代に変わることもありません。
これからの時代、心を育てる時間とプロセスをひとつひとつを大切にしていかないと、人間の心はどんどん狭くなり想像力と行動力を失い、やがてAIが人間を支配する時代になりかねません。
情報技術やAIが高度化してくるこの時代だからこそ、人間の心を見つめ育て直す必要があるのではないでしょうか。
時間とは生きること
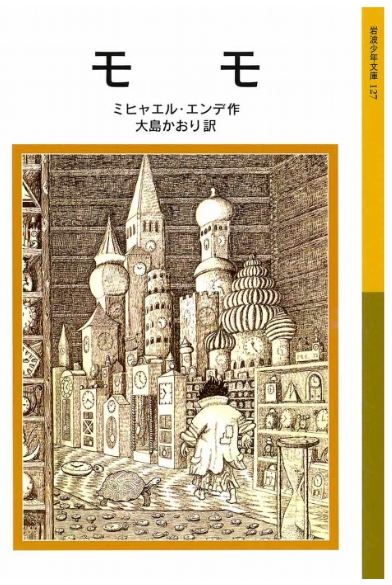
最後に、ミヒャエル・エンデのモモの一節をご紹介します。
時間をケチケチするという事は、本当は全然別のなにかにケチケチしている事に誰ひとり気付いていないどころか、自分達の生活が日ごとにまずしくなり、日ごとに画一的になり、日ごとに冷たくなっている事を誰ひとり認めようとはしない。
けれど、時間とは生きるというそのものなのです。
そして、人の命は心を住みかとしているのです。
人間が時間を節約すればするほど生活はやせ細っていくのです。
~ミヒャエル・エンデ ”モモ”より抜粋~
時間とは生きるというそのもの
時間をケチりはじめると、生きていることをケチりはじめ、より結果を求めはじめる
大人達は、余暇の時間でさえ少しの無駄もなく使わなくてはと考えました。
ですから、その時間のうちにできるだけたくさんの娯楽を詰め込もうと、もうやたらとせわしなく遊ぶのです。
だから、もう楽しいお祭りであれ、厳粛な祭典であれ、ほんとうのお祭りはできなくなりました。夢を見るなど、ほとんど犯罪も同然です。
けれど一番耐えがたく思うようになったのは、静けさでした。
自分達の生活が本当はどうなってしまったのかを心のどこかで感じとっていましたから、静かになると不安でたまらないのです。
ですから、静けさがやってきそうになると、そうぞうしい音をたてます。
けれども子どもの遊び場のような楽しげなさわぎではなく、怒り狂ったような、不愉快な騒音です。この騒音は日ごとに激しくなって、大都会に溢れるようになりました。
仕事が楽しいとか、仕事への愛着を持って働いているかなどということは、問題ではなくなりました。むしろ、そんな考えは仕事のさまたげになります。
大事なことはただひとつ、できるだけ短時間に、できるだけ沢山の仕事をすることでした。
~ミヒャエル・エンデ『モモ』より引用~
やがて、生きている時間(実感)を見失ってしまうと、最後は「致死的退屈症」という病気になる。
「灰色の男」の死んだ時間を人間が受け取ると、人間「致死的退屈症」という病気になる。
「はじめのうちは気付かない程度だが、ある日急に何もやる気がなくなってしまう。
何についても関心がなくなり、何をしても面白くない。
この無気力はそのうち少しずつ激しくなっていく。日毎に時を重ねるごとにひどくなる。
気分はますます憂鬱になり、心の中はますます空っぽになり、自分に対しても世の中に対しても、不満が募ってくる。
そのうちに、こういう感情さえなくなって、およそ、何も感じなくなってしまう。
何もかもが灰色で、どうでもよくなり、世の中はすっかり遠のいていてしまって、自分とはなんの関わりもないと思えてくる、怒ることもなければ、感激することもなく、喜ぶことも悲しむこともできなくなり、笑うこともなくことも忘れてしまう。
そうなると、心の中は冷え切ってもう一切愛することができない。
~ミヒャエル・エンデ『モモ』より引用~
まとめ
大地に種を蒔いて、その種が実りに変わるまでは時間がかかるもの。
その時間を「待たされている時間」と捉えるか、それとも「成長している時間」と捉えるかで、日常を「退屈」に感じるか、それとも「楽しみ」に感じるかは変わります。
最近の広告は「楽に」「すぐに」「かんたんに」がキャッチフレーズとして多く使われています。それだけ、楽ですぐにかんたんな結果を求めている人が多いのでしょう。
しかし、楽ですぐに得た結果は、かんたんに失うものがほとんど。
だから、どんなに情報が高速化されようとも「心を育てる時間」をケチってはならない。
その時間が、生きるということだから。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
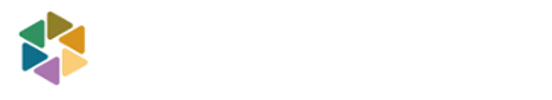
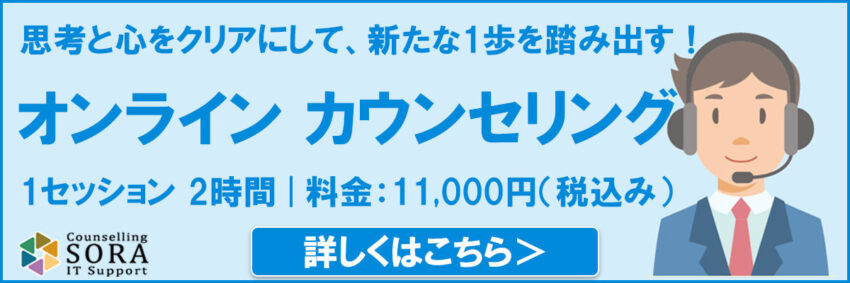

コメント