みなさん、こんにちは。
ライフカウンセリングSORAの関口です。
今回は「読書学」の4冊目です。
4冊目は岸見一郎・古賀史健著の「嫌われる勇気|自己啓発の源流「アドラー」の教え」です。
目的論と原因論の違いとは?
 アドラー心理学では原因論ではなく目的論で心や動機を捉えていく。
アドラー心理学では原因論ではなく目的論で心や動機を捉えていく。
アドラー心理学では、 過去の「原因」ではなく、いまの「目的」 を考えます。
私たちは過去のマイナスの出来事に対して「あれが起きたせいで、今がこうなった」という考え方をする。
しかし、これは「過去を後悔し今を否定する」原因論の考え方。
目的論の考え方は逆で、いまマイナスの出来事が起きたとき、それを否定する理由が欲しいから、過去のマイナスを持ってくるという考え方。
人が過去に原因を求めるときは、必ず今がうまくいっていないとき。
ただ、上手く行かない原因が「自分にある」と認めたくないから、過去の出来事を今にもってくる。
いかなる経験も、それ自体では成功の原因でも失敗の原因でもない。
われわれは自分の経験によるショックいわゆるトラウマに苦しむのではなく、経験の中から目的にかなうものを見つけ出す。
自分の経験によって決定されるのではなく、経験に与える意味によって自らを決定するのである。
恐い思いをしたとき、失敗をして恥ずかしい思いをしたとき、そのマイナスの思いはしっかりと記憶に焼きつく。
しっかりと記憶に焼きついてしまうから、また同じようなシチュエーションが訪れたときに、必ず「恐い」と感じる。
そのときに、「過去にも同じ思いをしたから私はできない」と考えると原因論になる。
問題は「なにがあったか」ではなく、「どう解釈したか」である。
確かに、その当時は恐い思いや恥ずかしい思いをしたのかもしれない、しかし、時間と共に人は成長し環境も変わっていくもので「また、同じような思いをする」とは限らない。
過去に「なにがあったか?」ではなく、これから「どうしていきたいか?」という考えを持つことが目的論の本質になると思う。
大切なのは何が与えられているのかではなく、与えられたものをどう使うかである。
ライフスタイルとは?
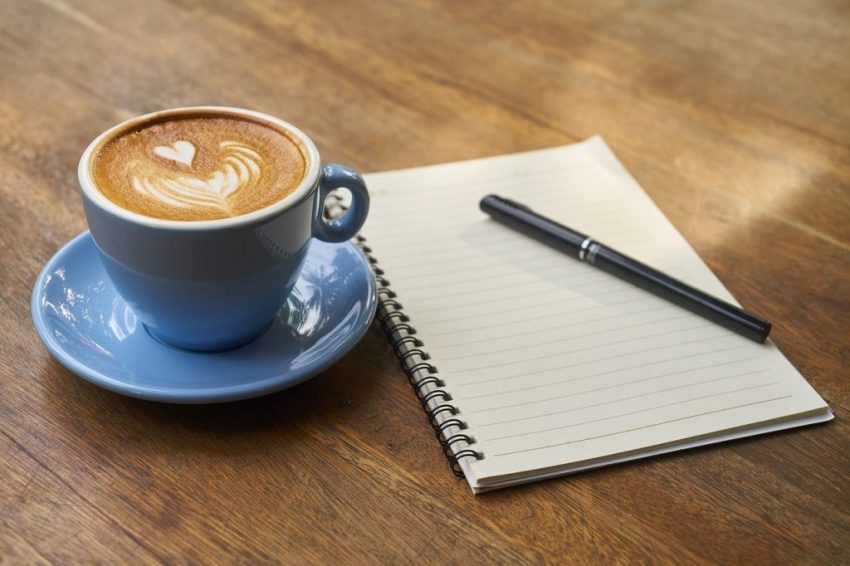 アドラー心理学のライフスタイルとはなにか?
アドラー心理学のライフスタイルとはなにか?
アドラー心理学では、性格や気質のことを「ライフスタイル」ということばで説明します。
~中略~
その人が「世界」をどう見ているか。また「自分」のことをどう見ているか。
これらの「意味づけのあり方」を集約させた概念が、ライフスタイルなのだと考えてください。
「性格を変えたい」と思っている人がいるが、「意味づけのあり方」を変えない限り、性格を変えても何も変わらないのではないだろうか。
ライフスタイルが先天的に与えられたものではなく、自分で選んだものであるなら、再び選びなおすことも可能なはずです。
人生がうまくいかないとき、周りや環境、性格を変えようとするのではなく、今までのライフスタイルを選びなおすとき。
アドラー心理学は、勇気の心理学 です。
あなたが不幸なのは、過去や環境のせいではありません。
ましてや能力が足りないのでもない。
あなたには、ただ〝勇気〟が足りない。
勇気とは、今までのライフスタイルに気づき、それを受け入れ、これからのを新しいライフスタイルを選びなおすこと。
まずは「いまの自分」を受け入れてもらい、たとえ結果がどうであったとしても前に踏み出す勇気を持ってもらうこと。
ライフスタイルを選びなすことが「自分を変える」ということ。
健全な劣等感とは?

私たちが感じる劣等感には「健全な劣等感」と「劣等コンプレックス」がある。
最初に劣等コンプレックスとはなにか?
劣等コンプレックスとは、自らの劣等感をある種の言い訳に使いはじめた状態のことを指します。
劣等コンプレックスは、「劣等コンプレックス」と「優越コンプレックス」の2つに別けることができる。
「劣等コンプレックス」の例としてあげられるのが、「どうせ、私は~ができない」と言うセリフ。
できない自分を自己正当化しつつ、周りに言い訳をする。
「優越コンプレックス」の例としてあげられるのが、自分が得意なところと相手が苦手なところを比べて、自分の優越感を満たそうとする人。
しかし、その本質は自分の劣等感を隠すためにしているだけ。
あたかも自分が優れているかのように振る舞い、偽りの優越感に浸るのです。
続いて、健全な劣等感とはなにか?
健全な劣等感とは、他者との比較のなかで生まれるのではなく、「理想の自分」との比較から生まれるものです。
私たちが自分と他人を比べる本当の目的は、「理想の自分」と「今の自分」のギャップを知るため。
「理想の自分」とのギャップを知ることで、ギャップを埋めること、すなわち自分自身を成長させていくために必要な行動が見えてくる。
われわれが歩くのは、誰かと競争するためではない。
いまの自分よりも前に進もうとすることにこそ、価値があるのです。
自分と他人を比べるのは「自分の理想」を知るため。
それが健全な劣等感の考え方。
人生のタスクとは?

人生のタスクを理解するには、アドラー心理学の目標を理解する必要がある。
行動面の目標が、次の2つ
1.自立すること
2.社会と調和して暮らせることそして、この行動を支える心理面の目標として、次の2つ
1.わたしには能力がある、という意識
2.人々はわたしの仲間である、という意識
人生において、これらの目標を達成するために必要になるのが人生のタスク。
アドラーはこれらの過程で生まれる人間関係を「仕事のタスク」「交友のタスク」「愛のタスク」 の3つに分け、まとめて「人生のタスク」と呼びました
アドラーが行動面と心理面の目標を掲げるのは、人間は「それが正しい」とわかっておきながら、実際にはそれができないから。
きっと、アドラーが掲げる目標は生涯をとおしても達成できなこと。
だからこそ、私たちは日々の人生において自分の「人生のタスク」に、向き合っていくしかない。
アドラーは、 さまざまな口実を設けて人生のタスクを回避しようとする事態を指して、「人生の嘘」と呼びました。
原因論で、問題の原因は「わたし以外」にあると考え、劣等コンプレックスで自己正当化することが「人生の嘘」になる。
では、人生のタスクに向き合うためには、具体的にどうすればいいのだろうか?
課題の分離とは?

自分自身の人生のタスクに向き合うために必要になるのが「課題の分離」という考え方。
人生のタスク=自分の課題
「課題の分離」をひと言でいえば、自分の課題に責任をもつということ。
自らの生について、あなたにできるのは「自分の信じる最善の道を選ぶこと」それだけです。
一方で、その選択について他者がどのような評価を下すのか、これは他者の課題であって、あなたにはどうにもできない話しです。
自分の人生のタスク(課題)と、相手の人生のタスク(課題)を明確に分離したうえで、お互いがお互いの人生のタスクに向き合っていくことが、対人関係では重要になる。
他者の期待を満たすように生きること、そして自分の人生を他人任せにすること。
これは、 自分に嘘をつき、周囲の人々に対しても嘘をつき続ける生き方なのです。
自分のタスクを他人に解決してもらったり、他人のタスクを解決してあげたりすると、その関係性は依存状態に陥る。
自分を変えることができるのは、自分しかいません
自分の人生のタスクを受け入れ向き合うことで、心は自由になれる。
自由とは、他者から嫌われることである
「嫌われる勇気」というタイトルに勘違いしてはならないことがある。
それは「嫌われてもいい」ということではなく、自分の言動に責任を持つということ。
なぜならば、自由とは自分の人生に責任をもつことだから。
「嫌われてもいい」と聞いたとき「もう、対人関係で我慢することをやめて、自分勝手に生きていいんだ~」と勘違いする人がいる。
しかし、アドラーは以下のように語っている。
課題の分離は、対人関係の最終目標ではありません。むしろ入口なのです。
人間関係で大事なことは、相手から嫌われるかどうかではなく、自分の言動に責任を持てるかどうか。
自分が責任を持てる言動をした結果、相手から嫌われてしまったのであれば、それはあきらめがつくこと。
他者の評価を気にかけず、他者から嫌われることを怖れず、承認されないかもしれないというコストを支払わない限り、自分の生き方を貫く事はできない。
つまり、自由になれないのです。
共同体感覚とは?

共同体感覚とは対人関係のゴールになる考え方。
他者を仲間だと見なし、そこに「自分の居場所がある」と感じられることを、共同体感覚といいます。
では、共同体感覚を感じられるようにするためにはどうすればいいのか?
そこで必要になるのが、「自己受容」と「他者信頼」、そして「他者貢献」の3つ になります。
「自己受容」は、今の自分自身を受け入れること。
「他者信頼」は、今の相手をそのまま受け入れること。
そのうえで「他者貢献」は、相手に対して今の自分が貢献できることはなにかを考え行動すること。
「他者貢献」の行動目的は、相手の為にするのではなくあくまでも自分自身のためにすること。
なぜならば、相手のための行動は相手の人生のタスクに踏み込む可能性があるから。
あくまでも、他者貢献も自分の人生の課題であることを常に意識しておくこと。
他者貢献とは、「わたし」を捨てて誰かに尽くすことではなく、むしろ「わたし」の価値を実感するためにこそ、なされるものなのです。
お互いがお互いの人生のタスクを明確にし、お互いがお互いのタスクに向き合っていくことで、人間関係は「依存」ではなく「協力」の関係性を築くことができる。
人生の意味とは?
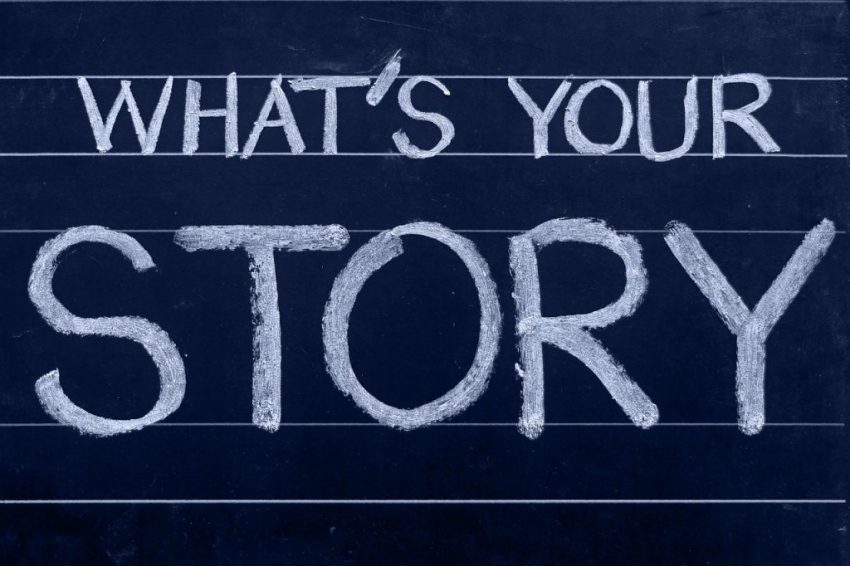
われわれは困難に見舞われたときにこそ前を見て、「これからなにができるのか?」を考えるべきなのです。
人生のタスクに向き合うことにどんな意味があるのだろうか?
アドラーは「一般的な人生の意味はない」と語ったあと、こう続けています。「人生の意味は、あなたが自分自身に与えるものだ」
人間はうまくいっているときは何も考えないし、何かの意味を見出すこともできない。
逆に、うまくいっていないときに一生懸命に考えて何かの答えを見つけようとする。
そして、一生懸命に考えた結果何かの答えを見つけたとき、うまくいかなかった出来事は初めて意味を見出すことができる。
人生の意味は後からついてくるのも。
だから、自分の人生と向き合い考えながら今ここを生きていくことが大事。
「わたし」が変われば「世界」が変わってしまう。
世界とは、他の誰かが変えてくれるものではなく、ただ「わたし」によってしか変わりえない。
まとめ
アドラー心理学は、言い訳ができない心理学だと思う。
人生で起こるすべてのことは「人生のタスク」であり、そのタスクに向き合うことが「人生の意味」につながっていく。
一時期、アドラー心理学が流行ったが、アドラーが心理学を通して1番伝えたかった「一人一人が自分の人生と向き合う」ということは浸透していないように感じます。
本のタイトルは「嫌われる勇気」ですが、本の実際の内容は「自分の人生との向き合い方」について書かれている本だと感じました。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
■引用元 「嫌われる勇気」 岸見一郎・古賀史郎著
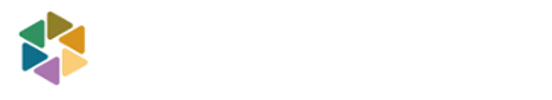
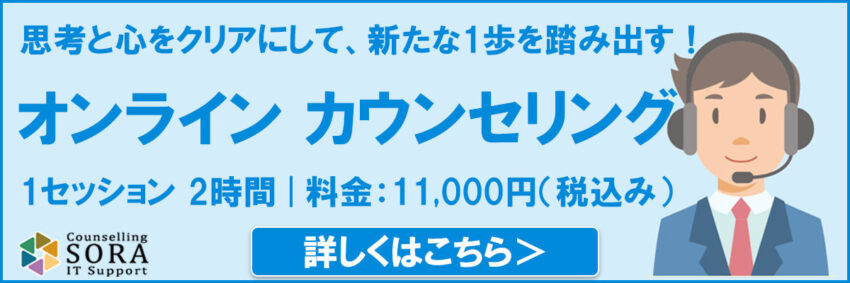


コメント