
カウンセリングSORAの関口です。
これまでの自分自身の人生を振り返るとともに、多くの方々から寄せられた人生相談を思い返す中で、私は「人生をより良く生きるためには、人としての生き方を学ぶことが大切だ」と実感しています。
人としての生き方を知ることで、これから歩むべき道が少しずつ見えてくるからです。
そこで、みなさまの人生に少しでも役立つヒントをお届けできればと思い、人としての生き方に学べる書籍を引用しながらブログを綴っています。
しばらくの間は、「イソップ寓話」からの引用をもとに、生き方について一緒に考えていきたいと思います。
今日の言葉
イソップ寓話より引用
173)木樵(きこり)とヘルメス
ある男が川の側で木を伐っていて、斧を飛ばしてしまった。斧が流されたので、土手に坐って嘆いていると、ヘルメスが隣れに思ってやって来た。そして泣いている訳を聞き出すと、まずは潜って行って、男のために金の斧を持って上がり、これがお前のものかと尋ねた。それではないと答えると、二度目には銀の斧を持って上がり、飛ばしたのはこれかと再び訊いた。男が首を振るので、三度目に本人の斧を運んで来ると、これこそ自分のだと言うので、ヘルメスは男の正直なのをして、三つとも授けた。
男は押し戴くと、仲間の所へ行って、一部始終を語った。聞いた一人が羨ましくなって、自分も同じ目に遭いたいと思う。そこで斧を取り上げると、例の川に出かけ、木を伐りながらわざと斧先を渦に投げ入れて、坐って泣いていた。
ヘルメスが現れ、どうしたのかと訊くので、斧を失くしたことを語った。ヘルメスが金の斧を持って上がり、失くしたのはこれかと尋ねたところ、男は先走りして、正にそれだと答えた。神はこれを与えなかったばかりか、自分の斧も返してやらなかった。神意は正しい者の味方をする、そして同じ程度に悪人の敵にまわる、ということをこの話は説き明かしている。
【引用元 岩波文庫 イソップ寓話集 著 イソップ 翻訳 中務哲朗】
「金の斧・銀の斧」に学ぶ―欲張らず正直に生きることの大切さ
「金の斧・銀の斧」の寓話は、欲張らずに正直に答えることの大切さを教えています。
イソップ寓話の魅力は、このシンプルな教訓を物語の形で伝えている点です。寓話だからこそ、子どもの心に響き、大人になっても記憶に残るのでしょう。
きっと、皆さんの心の中にも「金の斧・銀の斧」の物語は刻まれていることと思います。
イソップ寓話は紀元前6世紀(およそ2600年前)に生まれたといわれますが、現代まで語り継がれているのは、人間の本質が何も変わらないからだと感じます。
私の記憶にある「金の斧・銀の斧」では――正直な男が神から金の斧をもらうのを見た欲深い男が、自分の斧をわざと川に落とし、金の斧を求めた結果、すべてを失う――という展開でした。
しかし、原典では正直な男が神とのやり取りを仲間に語る場面があります。
もしそのとき「正直に答えたから金の斧をいただけた」と説明していたら、欲深い男は斧を失わずに済んだかもしれません。
もっとも、それでは寓話としての教訓は成立しなかったでしょうが……。
今日の問いかけ
「あなたは、日常の中のさまざまな問いに、正直に答えられていますか?」
私自身も、日々の生活の中で多くの問いかけや判断に直面します。
そのとき、打算的になって正直な思いを押し殺してしまうこともあります。
そんなときこそ「金の斧・銀の斧」の寓話を思い出したいものです。
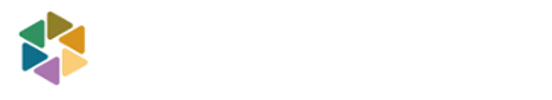
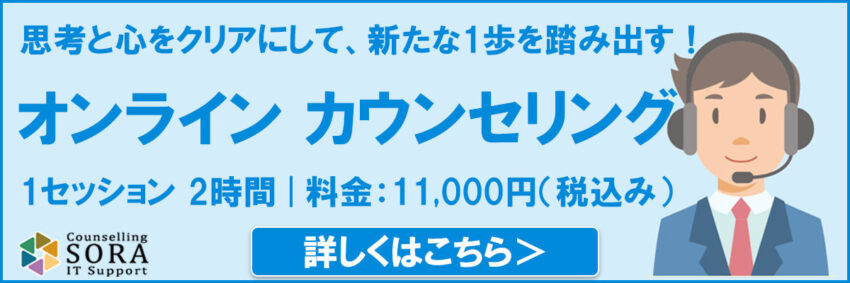


コメント