みなさん、こんにちは
ライフカウンセリングSORAの関口剛史です
組織では、年功序列制度から成果主義へシフトし、どれだけ長く会社にいたのか?ではなくどれだけ多く成果を出したのかで評価されるようになりつつあります。
しかし、最近は成果主義という名の結果主義が増えていて、このまま結果主義が優先されると、日本社会の荒廃につながると思います。
今日はアリの社会を参考にしながら「結果主義社会から三方よし社会へ」について考えていきます。
アリの社会は成果主義?
先日、公園でお菓子のカスを一生懸命運んでいる1匹のアリを見つけた。

人間から見れば小さなカスだけれど、アリからみれば自分の体ほどある獲物を一生懸命に運んでいる。
このアリはどこまで運ぶのだろう?と観察開始。
巣までの長い道のりを紆余曲折しながら一生懸命に運ぶ
途中、何度か奪われそうになっても絶対に獲物を離さない

大きな獲物をチームで運ぶアリを横目に見ながら、そのアリは一人で運び続ける

しかし、巣が近づいてきたときに異変が起きた
巣の周りにいた数匹との奪い合いがはじまり、最後に獲物を奪われてしまった。

獲物は奪い合いに勝ったアリが巣に持ち帰り、ここまで頑張ってきたアリは、また獲物を求めに離れていった。

もし、アリの社会に成果主義なるものがあれば、誰が1番評価されるのだろうか?
成果主義と結果主義のちがい
 日本の社会でも、年功序列制度が終わり成果主義が導入されつつある。個人的には、成果を得たプロセスが明確で評価基準がしっかりしていれば成果主義の考えはいいと思う。
日本の社会でも、年功序列制度が終わり成果主義が導入されつつある。個人的には、成果を得たプロセスが明確で評価基準がしっかりしていれば成果主義の考えはいいと思う。
成果主義では、成し遂げた結果とそれまでの過程が含まれるもの。秋に米を収穫するには、春に田を耕し種を蒔き、夏に雑草を抜く過程があって、はじめて秋に実りという成果が得られるよう、仕事の成果主義でも、その成果を得たまでの過程も重要になる。
成果主義と似たものとして結果主義がある。
結果主義では、物事の結果のみで評価をする。米に例えるならば、秋の実りが何キロ収穫できたかでのみ評価され、どのように収穫されたかは評価されない。
成果主義は過程+成果で評価され、結果主義は結果(成果)のみで評価される。成果主義で失敗するのは、結果主義とのちがいを理解していないから。
今の日本では結果主義が優位になっている。例えば、仕事で「売上を100万円以上にする」や「契約を100名以上獲得する」というノルマがあり、そのノルマを達成することだけで評価されるのは結果主義。
結果だけで評価されるため、相手を騙して売上や契約数を伸ばしても評価される。結果主義の組織は、組織内が競争状態となり無理をしてでも売上や契約を伸ばそうとする。また、上司も結果で評価されるため、部下の不正や誤りを正すことができず、組織全体が結果主義になり会社が荒廃していく。日本郵政グループで不正販売が行われたのも結果主義の成れの果て。
また、最近は「何もしなくても痩せられます」とか「スマホ1台で100万稼げます」といったキャッチコピーがあふれている。これも結果主義の特徴。
売り手は、簡単に得られるような結果をイメージさせ、その過程を考えさせようとしない。買い手は、面倒な過程をやりたくないから、簡単な結果だけを得ようとする。そして、何十万円もの投資をして、結果として何も得られないようなビジネスが成立している。
結果主義は「結果を出すために必要なこと」であれば、商品を偽ってでも人を騙してでも結果を出そうとする。しかし、結果主義が続けばその社会は必ず荒廃する。
結果主義は必ず荒廃する

結果主義が続くと、その社会は必ず荒廃する。理由は、皆が疑心暗鬼状態になると同時に、結果(成果)を出すまでの過程を積み上げる能力が社会全体から失われるから。
アリの話に戻します。もし、アリの社会が最後に獲物を持ち帰った者のみが評価される結果主義だったら、その後は何が起こるだろうか。
まず、皆が巣の近場で餌を探すようになり効率よく多くの成果を上げようとする。あわよくば巣の近くで奪えばいいという考えを持つ者も現れる。その結果、巣全体(組織)で遠くまで餌を探しにことをやめ、その能力を失っていく。
餌が豊富な時期は、巣の周りだけでも成果を上げられる。しかし、秋・冬に近づくにつれて巣の周りでの餌が少なくなると、狭い範囲で少ない成果を求めて組織内で奪い合うことになる。そのとき既に組織として遠くまで餌を探す能力も新たな発想もない状態。
最後は、組織内で過剰競争が起きて誰かを騙してでも結果をあげようとするから、組織内が疑心暗鬼状態となり、その組織は荒廃していく。
最近の日本は結果主義が蔓延していると思う。
自分さえよければ・・・とりあえず結果さえ出せば・・・終わりさえよければ・・・と結果だけを求めて過程をないがしろにするから、詐欺が横行し相手を騙すようなセールストークやキャッチコピーが普通に使われている。
フォロー数やチャネル登録数の結果だけで評価して、何のために何を発信しているのかを問わないから、過剰な投稿が増え炎上が起きる。
結果主義の社会は必ず荒廃する。根を張らない米は実りの重みで倒れ腐るのと同様に、過程がない結果は結果を支えるだけの根拠も能力も備わっていないから。
結果主義から三方よし社会へ

滋賀県近江八幡の近江商人には「三方よし」という精神・考え方がある。
三方よしとは「買い手よし」「売り手よし」「社会よし」の3つのよしを満たすような商売をすること。三方よしには順序があり、最初に「買い手よし」次に「社会よし」最後が「売り手よし」になる。
結果主義優位の日本では「売り手よし」だけが優先され、買い手を騙し社会に悪影響を与えているが、これからは「三方よし」のような精神・考え方を取りもどす必要があるのではないだろうか。
「三方よし」のように3つを満たすような商売は、必ずひとつひとつの過程が必要になる。成果主義を導入する際も「買い手よし」「社会よし」を成果とすることで、結果として「売り手(会社)」が成長していくのだと思う。
まとめ
今の日本では結果主義が優位になっています。特に新型コロナウイルスの影響で社会不安が大きくなるなかでは、結果主義がさらに目立つようになると思います。
しかし、このまま結果主義が優位に進めば社会の荒廃につながります。
そうならないためにも「三方よし」のような精神と考え方を持ちながら、成果を出していく仕事のあり方が求められてくるのではないでしょうか。
ただ、「三方よし」で商売をするのは時間がかかりとても難しいこと。理想論なのかもしれない。
しかし、難しいことだからこそ、皆で知恵を出して考えるという過程がうまれて、はじめて成果につながるのだと思う。
本当の意味での「働き方改革」とは、結果主義から「三方よし」のような働き方にチェンジすることなのではないでしょうか。
アリの社会を観察しながら、そんなことを思いました。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
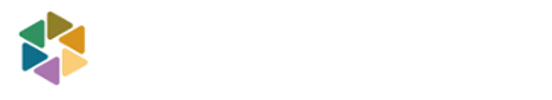
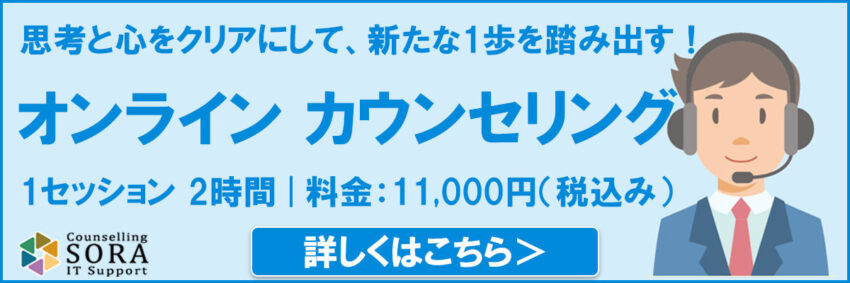

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 関連記事結果主義社会から三方よし社会へ […]